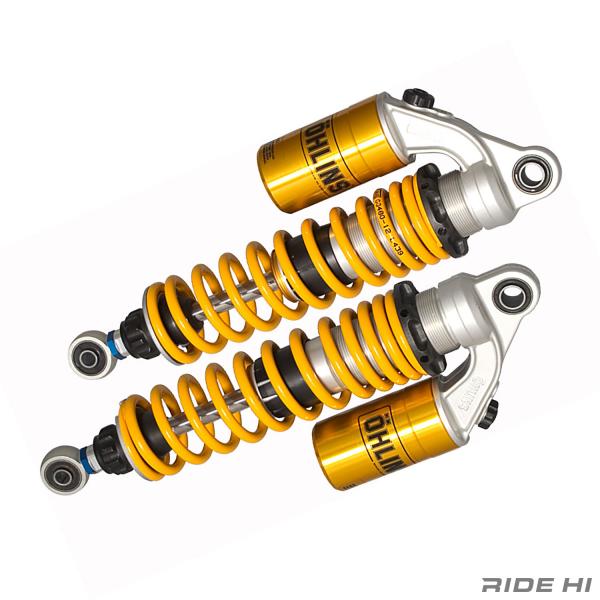クラシックはリヤタイヤをフロントに使う?
電子制御でますます高次元なパフォーマンスへ進化していく最新バイク。しかしそうした勢いにのまれることなく、緩やかに時が流れる、もしくは時間を止めたかのようなトラディショナルなバイクたちの人気も衰えない。
いかにも「オートバイ」らしい佇まいに、心がなごむライダーがどれだけ多いことか。エンジン、燃料タンク、シートとコンポーネンツが独立して凛とした風情に、変わらないモノへの安心感や信頼感が漂う。
そんなクラシカルなバイクたちに共通している”顔”がある。フロントタイヤだ。

日本ではTT100が定番
日本だとダンロップのTT100、あの伝統の英国マン島ツーリストトロフィーレース、略してT.T.レースのイメージを受け継いだネーミングのタイヤが有名だ。「ナニ履いてんの?、ティー・ティー、渋いねぇ」とそれだけで濃いファンであるのが伝わる定番タイヤ。
その特徴がフロントタイヤなのに、リヤタイヤと同じトレッドデザインであること。フロントタイヤといえば、デリケートな線の細いパターンが圧倒的なのに、TT100はリヤタイヤの彫りの深いどこか逞しいイメージのままだ。

ファントムも根強い人気
同じように、世界では次いでピレリのファントムもビンテージの領域では横綱クラス。こちらもリヤタイヤの溝が少ない、いかにも強そうな顔つきのままフロントに転用されている。
そうか、昔のバイクのつくり方だと、リヤタイヤがフロントに使えるんだ……と思いがちだが、これはまったくの間違い。たとえ履いているフロントタイヤと同じサイズが見つかったとしても、装着したらちょっと傾いただけでグイグイそちらへハンドルを取られる、とても扱えないハンドリングで乗れたものじゃなくなってしまうだろう。
そもそもフロントタイヤは、後輪の旋回を妨げずに助ける、路面追従性という大事な役割を担っていて、そのためにしなやかさを最優先したつくりになっているもの。
いまクラシカルなNewモデルでイメージ重視からリヤタイヤのようなトレッドデザインのTT100やファントムが装着されていても、構造的には低い荷重に反応する他のフロントタイヤと変わらない柔軟性に富んでいるはずだ。

DUCATI Paul Smart

DUCATI GT1000
ストリート・スクランブラーの流行りが
もたらしたリヤタイヤ”顔”のフロントタイヤ
しかし、やはり見た目にビンテージなバイクの”顔”は、このリヤタイヤのトレッドデザインが似合っている。
実はこのリヤタイヤの”顔”を使いはじめたのは’60年代から。それより前の世代では、それこそ創始期からタイヤの”顔”は真っ直ぐなラインが入っているだけの、いわゆるフロントタイヤのトレッドデザインが主流だった。
では何が起きたのか……ストリート・スクランブラーが流行りだしたからだ。
そもそもは英国のトライアンフやBSAなど、バーチカルツインのスポーツモデルを、アメリカのライダーたちがヒルクライムや非舗装のゲレンデで遊びだしたのがはじまりで、こうした環境ではストレートなグルーブ(溝)のフロントタイヤは泥に潜って都合が悪い。そこでサイズが細いリヤタイヤを嵌めて遊んでいたスタイルがストリート・スクランブラーとなったのだ。
そのスタイルはオフロードで凹まないようマフラーをセンターアップにたくし上げ、フロントにリヤタイヤのトレッドデザインのタイヤを装着していれば、フツーのスポーツバイクよりワイルドで逞しく見えた。

YAMAHA YDS-3C

KAWASAKI A1SS
これにアメリカへ輸出をはじめて成功を収めつつあった日本のバイクメーカーがこぞって倣った。ヤマハのYDS-3C、カワサキのA1SS、そしてホンダは燃料タンクまで専用にコンパクトにして他を突き放すセンスの良さをCL72(CB72ベースの250cc)で見せつけ大ヒットとなった。

ホンダCL72
これはある種いまのアドベンチャー系に通ずるものがあるかも知れない。
いわゆるオフロード専用モデルではなく、そうしたややサバイバルな世界に触れられる装備がワイルドで逞しさをアピールする。
快適で合理的なツーリング最速モデルや、いかにもハイエンドなスーパーバイクではないカテゴリーならではの、マイノリティな魅力といえるだろう。
いうまでもなく、アドベンチャー系も前後にオフロードタイヤ然としたトレッドパターンを履いている。タイヤは機能部品なのだが、こうした雰囲気づくりにも相応の役割を担っているのだ。